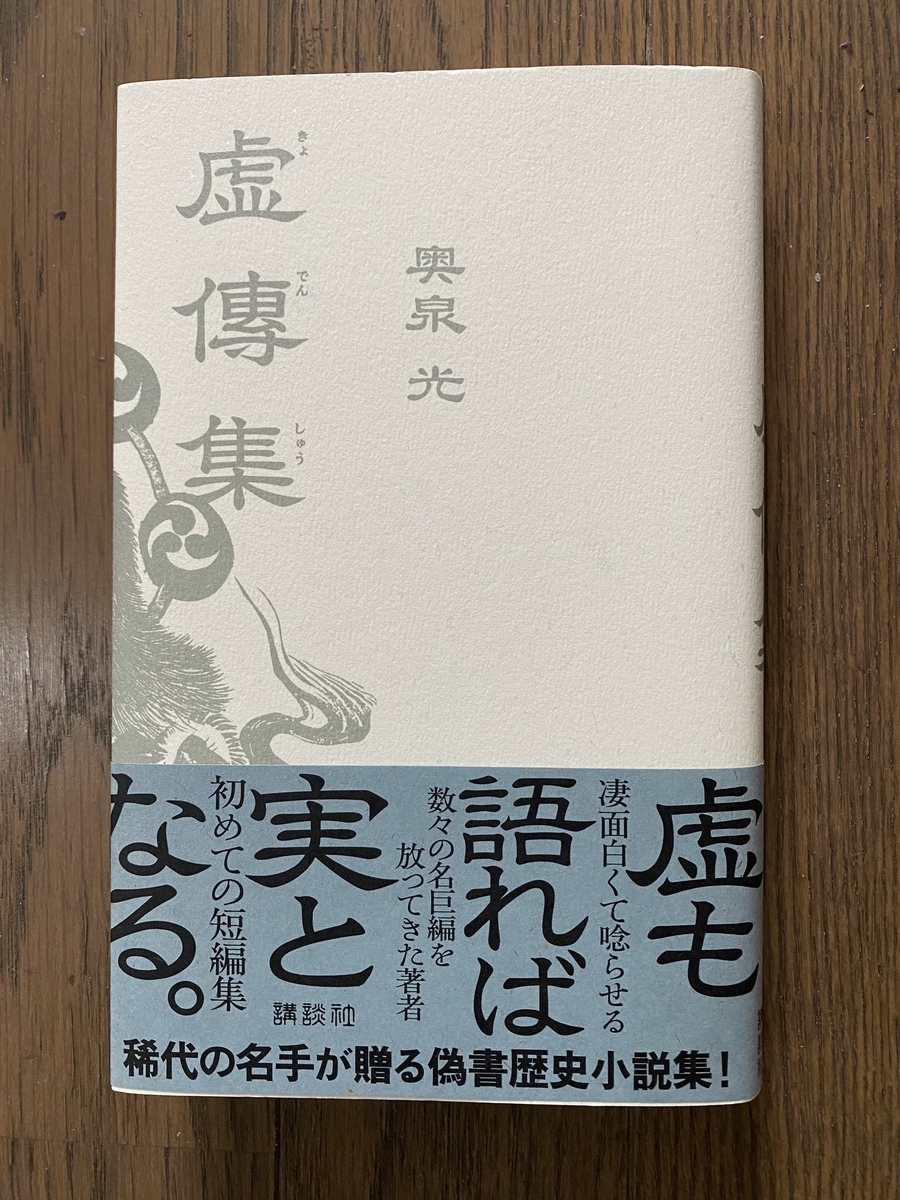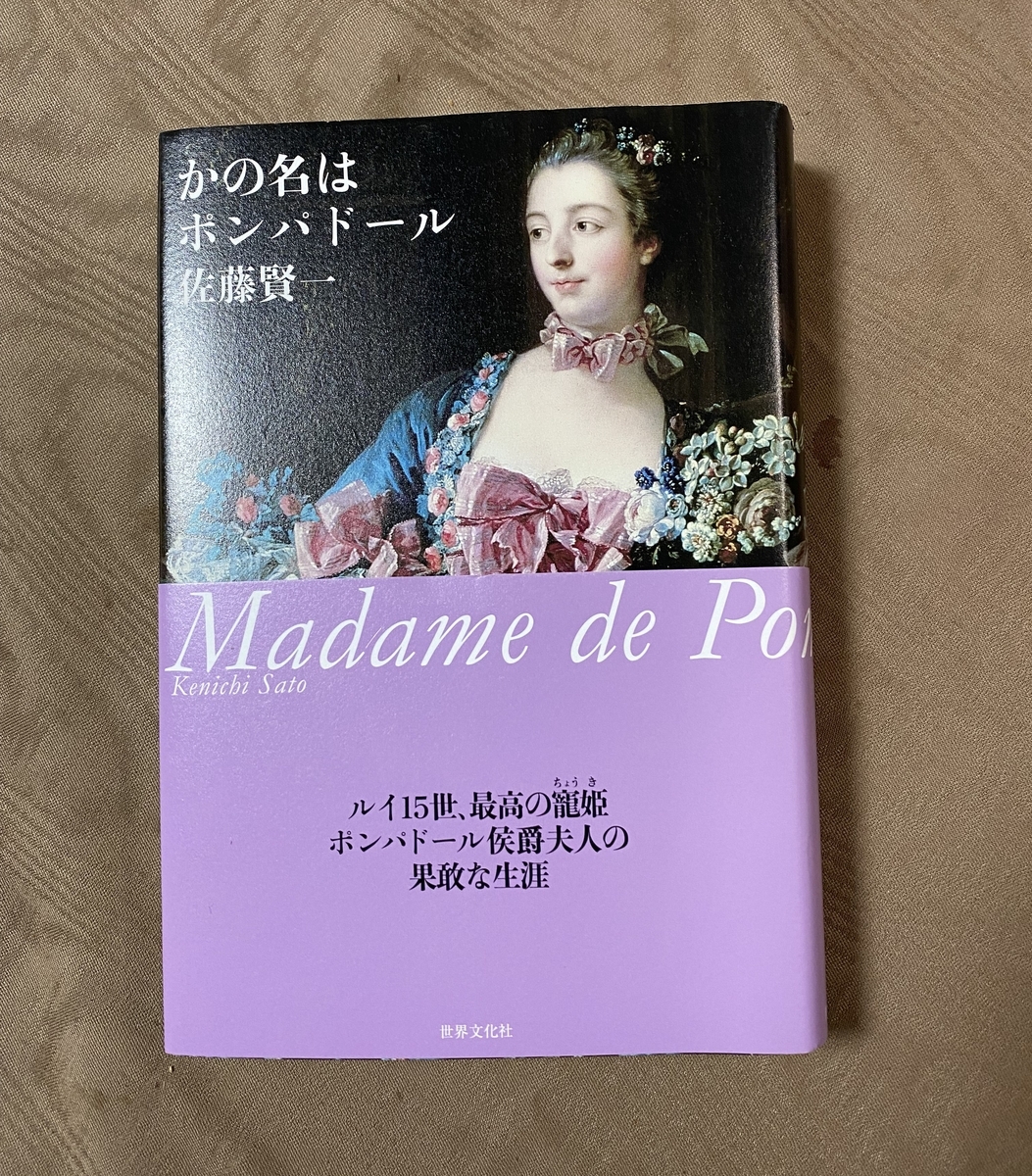大島真寿美氏の小説『渦』と『結』がおもしろかったので、他にどんな小説を書いているのだろうと、それ以前に書かれた『ピエタ』(ポプラ文庫、2014年)を読んでみた。2011年に出版され、本屋大賞第3位に選ばれた作品だ。

舞台は18世紀中期のヴェネツィア、なかでも、捨て子救済施設<ピエタ>がメインの舞台となる。そしてこのピエタと切っても切れないのが作曲家のヴィヴァルディ(1678年~1741年)。ヴェネツィアで生まれたヴィヴァルディは、1703年にカトリックの司祭に叙階され、直後にピエタの音楽教師に就任した。この時期のヴィヴァルディの作品は、ピエタのコンサートで演奏することを前提にして作曲されている。ピエタで育てられた才能のある女子は、ヴィヴァルディなどの教師から英才教育を受け、水準の高いコンサートを行って、その収益をピエタの維持費に充当していた。
物語は、ピエタで暮らしているアンナ・マリーアが、ヴィヴァルディが亡くなったという知らせを受け取り、それを親友のエミーリアに告げに来る場面から始まる。アンナ・マリーアとエミーリアは、ともに45年ほど前に捨てられた孤児で、ピエタで育ったが、音楽の才のあるアンナ・マリーアはピエタの合奏・合唱副長を務め、事務の才があったエミーリアはピエタの事務長のような仕事をしている。
ピエタの仕事に一段落をつけたエミーリアは、寄付をつのるため、大貴族の寡婦ヴェロニカを訪問するが、そこでヴェロニカから、裏に詩が書いてあるヴィヴァルディの自筆譜を探していると告げられ、それが見つかったら高額の寄付を行うともちかけられる。その先は、楽譜を探すためにエミーリアがさまざまなヴィヴァルディ関係者を訪ね、生前のヴィヴァルディについて話を聴くという展開になる。
そのなかの一人に高級娼婦クラウディアがおり、エミーリアは楽譜探しに加えて、ヴィヴァルディの知られざる一面を知りたいという好奇心からクラウディアを訪ねる。クラウディアと会い、その人柄や高い見識を知ったエミーリアは、クラウディアにヴェロニカを紹介する。クラウディア、ヴェロニカ、エミーリア、育った環境があまりにも違うこの3女性の対面が、ある意味でこの作品のハイライトだろう。それは、3女性が意気投合するのに身分の違いはなんの関係もないということだ。
「あの夜のことを思い出すと、わたしはなんとも言いようのない、不思議な心地がする。クラウディアさんもヴェロニカもすっかり打ち解け、いつしか、ぽっかりと時の流れに浮かんでいるような気持になったものだった。これまで一度も味わったことのない、そう、なんといったらいいか、温かいお湯にでもつかっているかのような安心感に包まれていた。」(本書233頁)
この出会いから物語の時間の進行は早くなり、クラウディアの病気、彼女に対するヴェロニカの手厚い介護、クラウディアの死へと進む。親しい人間だけによるその弔いの最中、ヴェロニカが探していた楽譜は意外なところから見つかる。楽譜探しやヴィヴァルディの秘められた個人史を探るという糸はあるが、全体としては、エミーリアを軸にした女性たちの心の交流を描いた作品といえる。
ふりかえって考えてみると、大島氏の小説は、『ピエタ』も『渦』も『結』も、悪人が登場しない。大島氏はいわゆる善悪対立で物語をすすめようとはしておらず、あえていえば人間同士の<融合>が感じさせる作風だ。そしてまた、大島氏の文体の特徴の一つに、会話を書くとき、直接話法と間接話法が入り混じった独特の話法をつかうということが挙げらる。直接話法と間接話法を混ぜ合わせることで、一人称と三人称の境目があいまいになり、いつの間にか登場人物たちの<融合>が生じているということなのかもしれない。