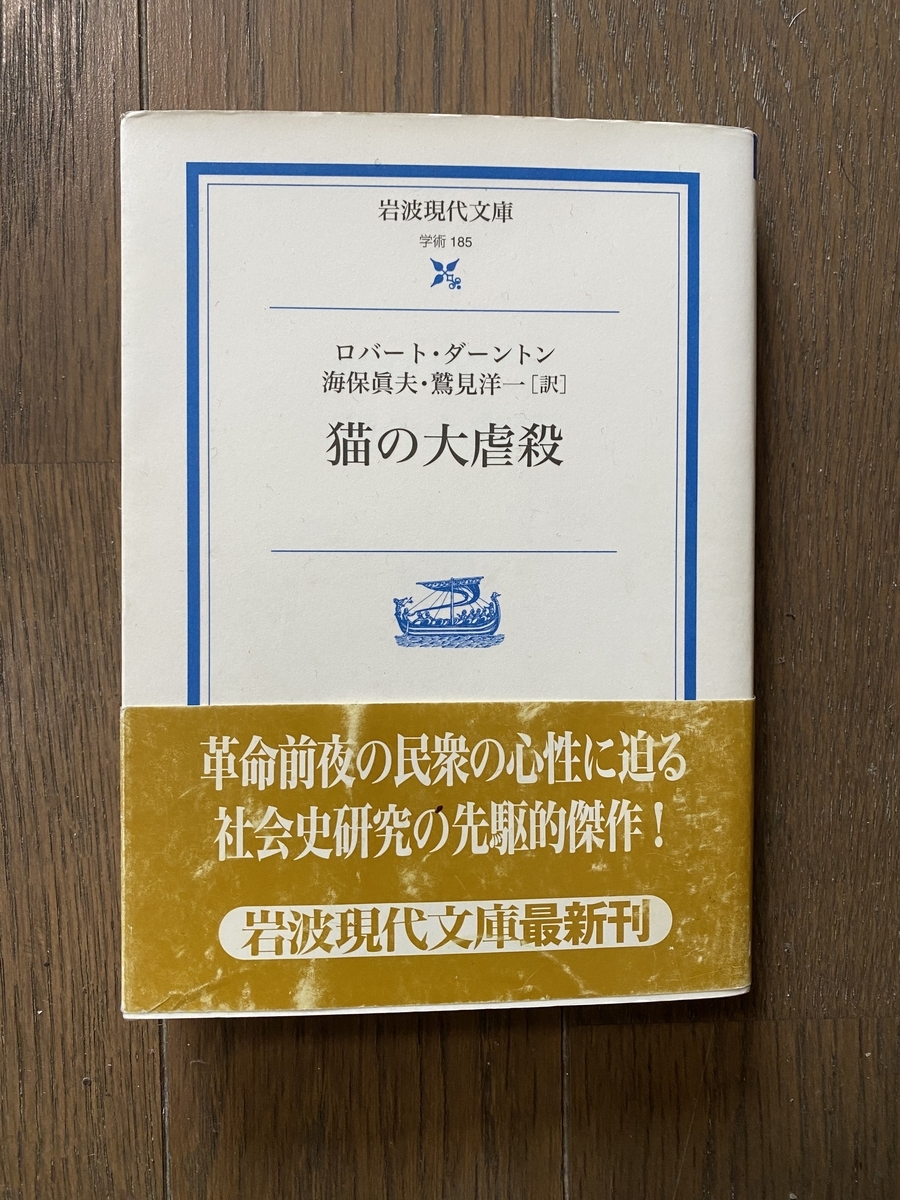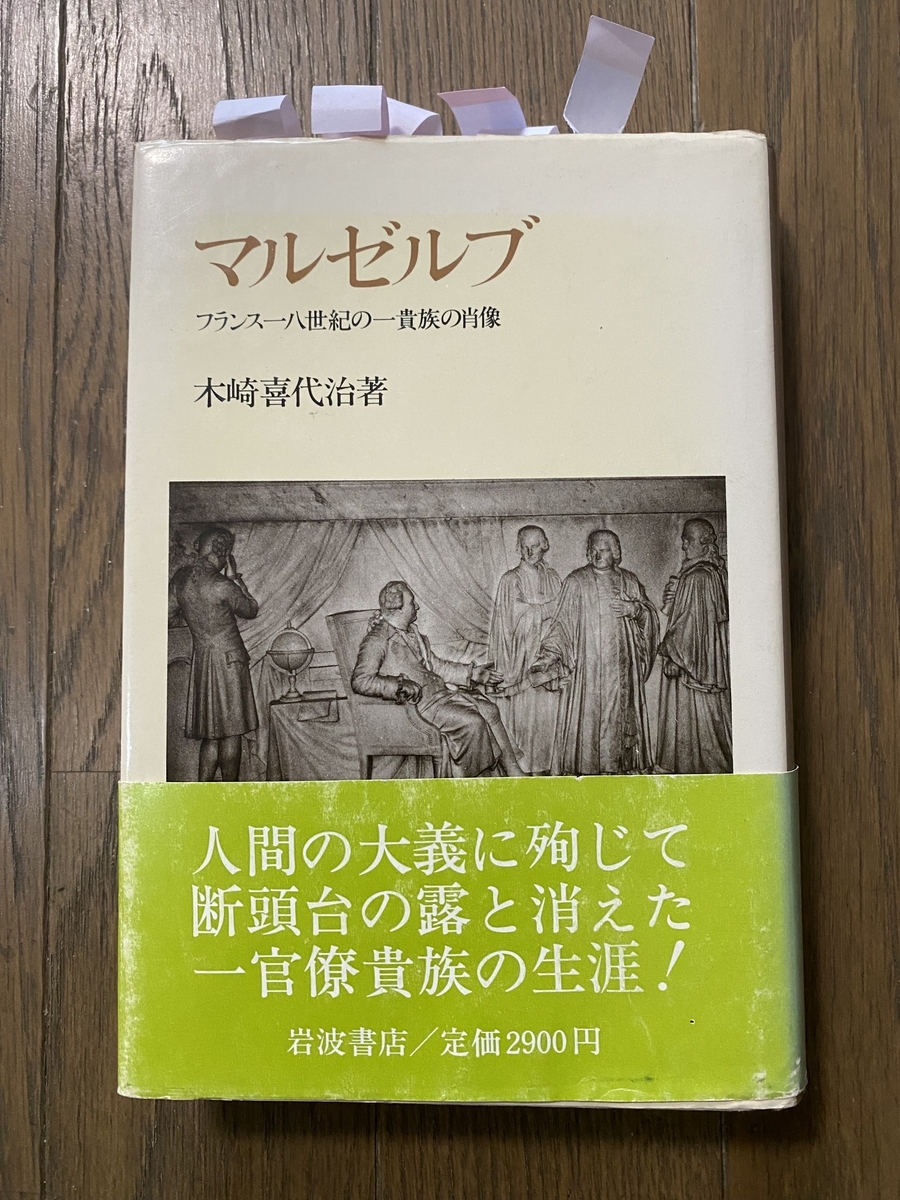今回は、いつもと少し趣向を変えて、18世紀フランスの冒険小説『セトス』に挑戦してみた。
この小説は、ジャン・テラソン師(1670年~1750年)の作品で、古代エジプトおよびアフリカ大陸を舞台にしている。ギリシア語で書かれた古代エジプトの歴史物語が見つかったのでそれをフランス語に翻訳し紹介するというふれこみで、1731年に出版された。大長編で、邦訳は、その一部である第8巻だけが、岩波書店「ユートピア旅行記叢書」第10巻に収載されている(永見文雄訳、岩波書店、2000年)。この作品は出版当時大好評で、テラソンは、『セトス』刊行直後にアカデミー・フランセーズ会員に選ばれている。また彼は当時の文学論争に加わったことでも有名で、『セトス』執筆以前の1715年、近代文学支持者として『ホメロスのイリアスに関する批判的論考』を書いている。

さて『セトス』の主人公は作品のタイトルになっているセトスで、彼は、古代エジプトにあった4王国のうち、メンフィスの王子という設定。テーベとの戦争で負傷するが一命をとりとめ、その後、アラビアから喜望峰を経てアフリカを一周し、その間さまざまな出来事に遭遇しながらエジプトに帰還する。奇想天外というしかない!
「ユートピア旅行記叢書」に収載されているのは、このうち、アフリカの西海岸にあるアトランティス王国を訪問した際のエピソード。この国は、名前からはアトランティス伝説を想起させるが、『セトス』のなかでは現在のモロッコの南方あたりに設定されている。このアトランティスの国制紹介がユートピア物語に相当するということで、アトランティス訪問のエピソードだけが抜き出されて、「ユートピア旅行記叢書」におさめられている。
そこでこの叢書の編纂者の意図にしたがってテラソンが描くアトランティス(ユートピア)の国制を簡単にみてみると、まず、アトランティスでは宗教が非常に重んじられており、「宗教を維持するには、何人かの個人の現実に存在する内面的な信仰心を頼りにするだけではけっして十分ではない、国民全体を結びつけるある種の儀式の外面をそれに付与しなければならない」(本書36頁)と考えられている。政体は選挙王政で、近隣の他の国とはほとんど交わらず、戦争も放棄している。国民は、市民、商人、職人の三階層からなる。奴隷は存在しない。市民の収入はもっぱら所有地と家屋による。経済をになうのは商人の階層だが、外国との交易は家畜と果物の交換程度で、それは王に紹介された世話役が行う。商人は世話役からしか商品を受け取らず、市民にしか小売りしない。職人は他の国と共通だが、貧困に苦しまないよう、困ったときには国家が生活を埋め合わせる。
アトランティスでセトスは、カルタゴから亡命している旧知の王子ジスコンに出会い、ジスコンを助けるたるアトランティスを後にする。この国での一連のエピソードのなかでは、ジスコンの妻ザリトの婦徳の描写が読みどころと言えよう。
以上が、「ユートピア旅行記叢書」におさめられている『セトス』のあらすじだが、これだけでは、作品全体がおもしろいのかどうか、私にはよく分からなかった。ただし出版当時は、さまざまな苦難や冒険を重ねながらセトスが成長していく一種の教育小説として読まれたらしい。

この作品の一種の後日譚として、ドイツの作家トビアス・フォン・ゲプラー(1726年頃~1786年)が英雄劇『エジプト王ターモス』を書いており、その劇には、若いモーツァルト(1756年~91年)が1773年に付随音楽を作曲している(K. 345)。また『セトス』の世界観は、『魔笛』(K. 620)にも影響を及ぼしているようだ。