ロバート・ダーントンの『猫の大虐殺』(1984年、海保眞夫、鷲見洋一訳、岩波現代文庫<岩波書店>、2007年)を読んだ。本書は最初、岩波書店から単行本として1986年に刊行されたが、私が読んだ岩波現代文庫版は、そのなかから第3章、第5章を省略して編集した簡略版。この現代文庫版は、「農民は民話をとおして告げ口する――マザー・グースの意味」「労働者の叛乱――サン・セヴラン街の猫の大虐殺」「作家の身上書類を整理する一警部――フランス文壇の分析」「読者がルソーに応える――ロマンティックな多感性の形成」の4章で構成されている。各章は独立した歴史的論考。主として17世紀から18世紀の史料を独自の観点から読み込んだもので、それぞれの章に直接的なつながりはない。全体をとおし、ダーントンは歴史の表面にはなかなか浮かび上がってこない一般的な人々に焦点をあて、そこから歴史の見直しを促している。
これに関して、岩波現代文庫版のために寄稿した序文のなかで、ダーントン自身が自分の意図について語っているので、まずそれを紹介しておこう。
「(猫の)虐殺にはいろいろ意味づけができ、それらの意味をさまざまに構築したり、結合したりできるのです。そうした複数の意味を、ミステリー小説の結末みたいに、たった一つの結論に還元してしまうのは、人間の営み一般について、また、18世紀に労働者がいかに主人を愚弄できたかということについて、誤解することにほかなりません」(本書viii頁)。ダーントンがこだわるのは、たとえば猫の虐殺という象徴的なできことの「複合性や多様性」(本書vii頁)だ。
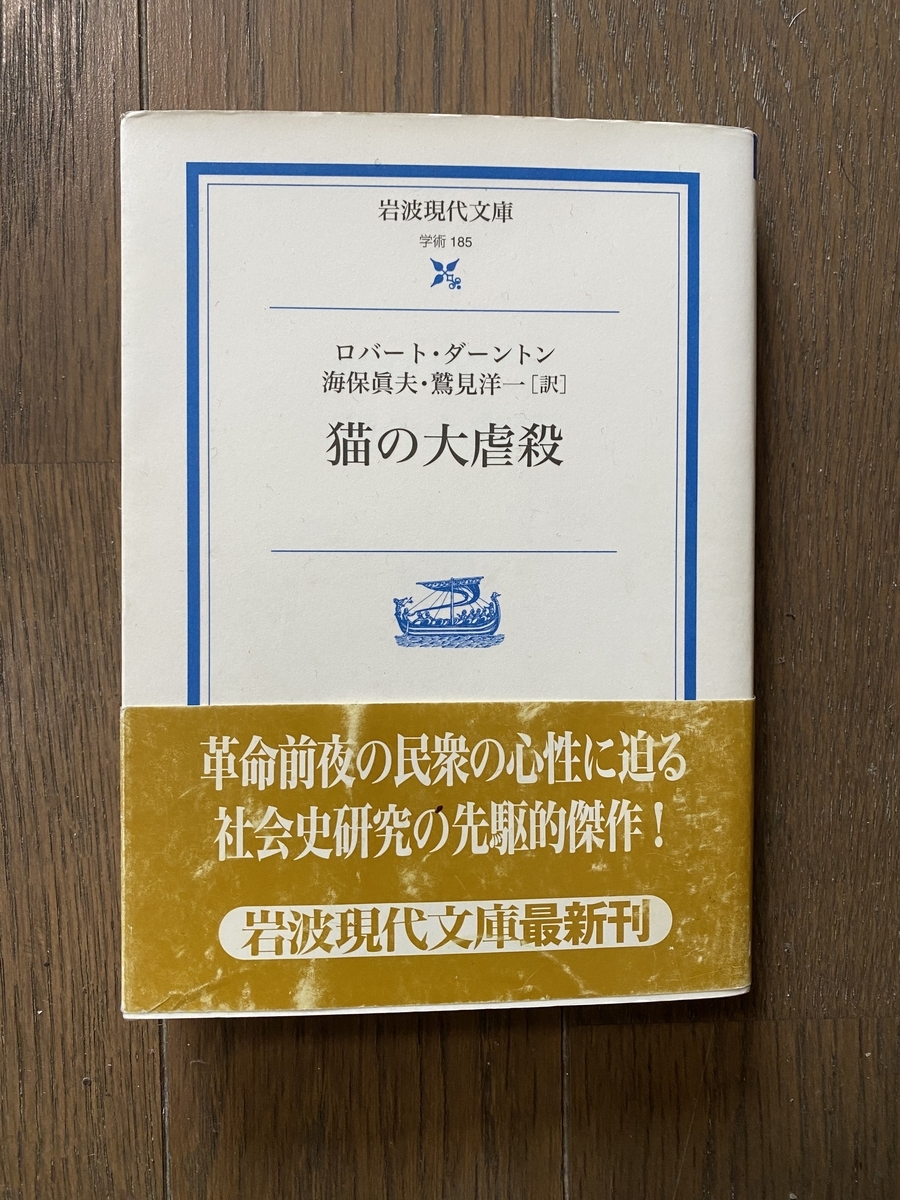
前置きはこのくらいにして、本書の内容を章ごとに追ってみよう。
「農民は民話をとおして告げ口する」は、いわゆるマザー・グースとして知られるヨーロッパ各地の民間に伝えられた童話の原型を模索し、それらを比較しながら、地域差やそうした違いを生じさせた民衆心理を明らかにしたもの。
「労働者の叛乱」は、18世紀前半にパリのサン・セヴラン街の印刷工場に徒弟奉公していたニコラ・コンタが残した猫の虐殺に関する手記から、当時の印刷工場の実態を探ったもの。ちなみに、印刷工は職業柄読み書きができ、したがって、機会があれば、自分の身の回りのことを書き残すことができた。本書全体の表題にもなっているので、猫の虐殺というできごとの顛末を簡単に紹介すれば、普段の待遇への不満から、雇い主の命令を口実に、印刷工が工場の周囲に棲んでいた猫や雇い主が大事にしていた猫を、まさに虐殺する話である。ダーントンによれば、「旧制度下のフランス人は、猫の唸り声を聞くと直ちに魔女、夜の饗宴、寝取られ男、嫌がらせの儀式、虐殺を連想した」(本書143~4頁)とのことで、この事件に限らず、18世紀当時、猫はカーニヴァルなどのさまざまな機会に殺されることが多かったようだ。18世紀は猫の受難の時代だったといえるかもしれない。
「作家の身上書類を整理する一警部」は、パリの警察に勤務し出版業を監視していた警部ジョゼフ・デムリが書き残した調査書類から、一流とはいえない名もない作家がどのような生活をしていたのかを拾い出したもの。
「読者がルソーに応える」は、フランス西部のラ・ロシェルに住んでいた商人ジャン・ランソンがヌーシャテル印刷協会(この協会の史料は、ダーントンのさまざまな研究にネタを供給する宝庫になっている)に宛てた書籍の注文書から、一般の読者がどのような書籍をどのように読んでいたかを探ったもの。注文書からはランソンがルソーの熱心な読者・崇拝者だったことが分かり、ルソーの何がランソンを魅了し、身銭を切って高価なルソーの書籍を購入させたのかに迫っていく。
個人的に一番おもしろく読めたのは「作家の身上書類を整理する一警部」の章。デムリは501人もの作家の身上調査書を残しており、さまざまな作家たちの外見的な特徴や彼らがどのように生活していたのかという実態が克明に分かるからだ。
まず風貌だが、ヴォルテールは「背が高く、冷ややかで、好色漢の風貌」(本書189頁)、ディドロは「中背、かなり品のいい人相」(本書234頁)などと、デムリは記している。
また作家たちの実態はといえば、「筆を執る者の尊厳とその使命の神聖さとは、既に作家の主目的として啓蒙思想家たちの著作に現れている。だが、デムリの調査書にはこうした観念は見当たらない。警察当局は作家の存在に気付くと分類し、その経歴を調査書類に記載はしたが、彼らを特定の専門職あるいは社会的地位の所有者とはみなしていない。作家たちはそれぞれ紳士、僧侶、法律家、あるいは従者なのであって、作家という独立した資格は存在しない」(本書209~10頁)のであり、また、「庇護者からの解放、文学市場の完全な自由化、著述への全面的献身といったものが作家のあいだにいまだ確立していない以上、伝統的な分類体系のなかに彼らを独立した存在として位置づけるのは不可能だった」(本書210頁)という。
さらに注目すべきなのは、次のような事実である。
「彼は作家を指すのにしばしば<少年(がルソン)>という語を用いている。この言葉は実年齢と葉無関係である。ディドロは当時37歳で、結婚して子供もいたが、それでも<少年>と言及されている」(本書210頁)。
目立つ仕事をしていても、一般的にみれば、作家は、世話の焼ける大きな子供に過ぎなかったのだろう。
こうした作家たちを日常的に監視しながらデムリは何を感じていたのだろうか。彼は、「革命を予見していたわけではない。だが、文芸共和国を検分して彼が感じたのは、高まる世論の敵意のまえに、王政が日毎弱体化していること」(本書224頁)であった。警察の力では、そうした弱体化を阻止することはできない。対症療法的に、目にあまる著作やその著者を摘発することだけだ。
しかし、「ディドロおよび彼と同臭の徒についてのデムリの調査書は、従来漠然としていた知識人の姿が次第に明確な輪郭を備えてきたことを示している。近世初期のフランスにおいて、知識人は無視し得ぬ力となりつつあった」(本書232頁)というのが、この章でのダーントンの結論である。